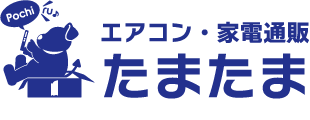電気自動車(EV)とガソリン車の違いとは?
ガソリン車といわれるガソリンなどの燃料で走行する自動車は、燃料を給油して燃焼させることでエンジンを動かします。そのため、走行中に二酸化炭素をはじめガスなども多く排出されてしまいます。
それに対し、電気自動車は車体に搭載されたバッテリーを充電することで、モーターを動かして走行します。ガソリンに変わり電気で車を動かすため、二酸化炭素を含むガスが排出されない環境に優しい自動車です。
「電気自動車は充電」、「ガソリン車は給油」が必要となる点も大きく異なります。給油スタンドの数は充実しており、給油時間も5分程度です。対して、電気自動車を充電できるスタンドの数はまだまだ少なく、急速充電の場合でも30〜60分ほどと長くかかります。
しかし、電気自動車のバッテリーは、災害時に電気製品への電力供給に活用できる利点もあるため、防災の観点からみるとメリットの多い自動車です。
電気自動車(EV)とガソリン車の維持費用の比較
電気自動車とガソリン車は、維持費も異なります。ここでは、さまざまな観点から維持費の比較について紹介します。
電気代とガソリン代
「電気代」と「ガソリン代」を、1万km走行した場合を想定して比較してみましょう。
比較のため「(1)電気代・ガソリン代の単価」、「(2)電気自動車・ガソリン車の性能」は以下のように設定し、これらの条件をもとに「(3)1万km走行時の比較」にてコストを算出しています。
(1)電気代・ガソリン代の単価
| 電気代の単価 | 31円/kwh |
| ガソリンの単価 | 174円/L |
(2)電気自動車・ガソリン車の性能
| 電気自動車 | 6.0km/kwh |
| ガソリン車 | 15.0km/L |
電気自動車とガソリン車のそれぞれ平均的な性能をもとにしています。
(3)1万km走行時の比較
| 電気代 | 5万1,677円 |
| ガソリン代 | 11万6,058円 |
【電気代の計算】
1万kmを走行するための電力量:「1,667kwh(= 1万km ÷ 6.0km/kwh)」
1万kmを走行するための電気代:「51,677円(= 1,667kwh × 31円/kwh)」
【ガソリン代の計算】
1万kmを走行するためのガソリン量:「667L(= 1万km ÷ 15.0km/L)」
1万kmを走行するためのガソリン代:「116,058円(=667L × 174円/L)」
電気代やガソリン代は単価の変動や車種の性能によって左右されますが、上記のように比較すると電気自動車のほうがお得だといえます。
自動車税・自動車重量税
自動車の車検を受けるために、「自動車税」と「自動車重量税」の2つを納付する必要があります。自動車税と自動車重量税について、それぞれの費用を比較します。
自動車税
「自動車税」は4月1日時点での車の所有者が、車検前の5月までに納める必要がある税金です。金額は、自動車のエンジン総排気量により設定されています。
【乗用車(自家用車)の自動車税】
| 種類 | 自動車税 | 総排気量 |
|---|---|---|
| 電気自動車 | 25,000円 | 1.0リッター以下 |
| ガソリン車 | 25,000円〜110,000円 | 1.0リッター以下〜 6.0リッター超 |
ガソリン車は車種によって総排気量が異なるため、「1.0リッター以下〜 6.0リッター超」と総排気量に応じて自動車税が設定されています。
一方で電気自動車の場合は、車種に関わらず排気量はゼロとなるため「1.0リッター以下」の扱いとなり、自動車税は一律で25,000円です。
さらに、電気自動車にかかる税金を減税する制度もあります。主に挙げられるのは、「グリーン化特例」と「エコカー減税」です。
「グリーン化特例」とは、環境性能がよい自動車は減税し、環境負荷が高い自動車は増税する制度です。新規登録した翌年の自動車税が対象で、電気自動車は75%が減税されるためさらにお得です。
「エコカー減税」も自動車重量税が減税される制度です。次に、自動車重量税にて詳しく解説します。
自動車重量税
「自動車重量税」は毎年かかる税金で、車の重量や経過年数に応じて税額が異なります。新規登録時に次回の車検までの3年分を支払い、それ以降は車検のタイミングで次回の車検までの2年分を支払います。
自動車重量税は以下の内容で決まります。
- 車両重量
- 自動車重量0.5トン単位で税額が異なります。
- 年数
- 新規の登録から13年が経過、さらに18年が経過すると税額があがります。
- エコカー減税
- 燃費性能や排気ガス性能に応じて自動車重量税に対し、25%〜100%の減税・免税がされる制度です。
【乗用車(自家用車)の自動車重量税】
| 種類 | 新規の登録時 | 初回の車検時 | 13年経過 | 18年経過 |
|---|---|---|---|---|
| 電気自動車 | 0円(免税) | 0円(免税) | 0円(免税) | 0円(免税) |
| ガソリン車(0.5t以下~3t) | 12,300円~73,800円 | 8,200円~49,200円 | 11,400円~68,400円 | 12,600円~75,600円 |
エコカー減税の措置により電気自動車の自動車重量税は一律で免税され、大きく負担が軽減されます。
車検費用
電気自動車は、ガソリン車と比べるとシンプルな構造をしています。そのため、点検内容や部品交換が少なくすみ、車検費用を抑えられる可能性があります。車検は新規登録から3年で初回車検、それ以降は2年ごとに車検を受けます。車検費用は「法定費用」、「基本費用」があり、それぞれ詳細の項目は以下のとおりです。
【車検費用(法廷費用)にかかる内容】
- 自動車重量税
- 車の重量や経過年数などに応じて納める税金です。エコカー減税の対象となる電気自動車は、免税されるため大きくコスト低減できます。
- 自賠責保険
- 自賠責保険は、加入が必須とされている保険です。一律の金額がかかり、購入時に3年分(36か月分)で23,690円、以降2年分(24か月)で17,650円の保険料を支払います。電気自動車とガソリン車に差異はありません。
- 印紙代
- 印紙代は1,400円〜2,200円ほどです。車検を受ける場所や自動車のサイズによって違いがありますが、自賠責保険と同じく電気自動車とガソリン車に差異はありません。
【車検費用(基本費用)にかかる内容】
- 車検基本料金
- 車検を依頼する業者によって異なりますが、電気自動車とガソリン車で金額はほぼ変わりません。
- 諸費用
- 整備にかかった部品代や作業工賃などです。電気自動車の場合、部品交換や検査が一部不要になることから、ガソリン車よりも諸費用が抑えられる可能性があります。しかし電動モーターなどの不備があれば諸費用に上乗せされるため、必ず安くなるというわけではありません。
バッテリー交換の費用
車のメンテナンスでは車検とは別に、車の部品を交換することもよくあります。ここではバッテリー交換について紹介します。
電気自動車
電気自動車の駆動に必要なバッテリーは、一定の劣化は避けられません。バッテリーの容量によって交換費用は大きく異なりますが、70〜90万円ほどとかなり高額です。ただし、電気自動車のバッテリー交換はメーカー保証があるため、保証期間内であれば無料での修理や交換が可能です。
国内の自動車メーカーの多くは、「8年経過または16万km走行」で「バッテリー容量の70%以上」を保証しています。「8年経過・16万km走行」は車の買い替えを検討してもよい時期のため、バッテリー交換を心配する必要はほぼありません。
ガソリン車
ガソリン車の場合、寿命となったバッテリーは交換しなければなりません。標準的なバッテリーは2年、高性能バッテリーは3年ほどで交換が必要です。標準的なバッテリー価格は4,000円ほど、交換作業代に3,000円ほどがかかります。
電気自動車(EV)とガソリン車の初期費用の比較
電気自動車とガソリン車の車体価格など、初期費用についても比較します。
自動車本体の価格
電気自動車の本体価格は、およそ300万円〜500万円ほどです。車種によっても異なりますが、ガソリン車の場合は100万円〜300万円ほどで新車が販売されているため、電気自動車の車体価格は比較的高い傾向にあります。
しかし、ガソリン車と同等の価格帯の車種も増えてきているため、「電気自動車は高い」というイメージは変わりつつあります。
EV(PHEV)には充電用設備の設置が必要
電気自動車は、充電設備を設置すれば自宅でも充電が可能です。電気自動車のなかには、100%電気エネルギーで走行するEVとは別に、ガソリンと電気の双方での走行が可能な「HEV(ハイブリットカー)」や「PHEV(プラグインハイブリッドカー)」があります。
PHEVはガソリン給油に加えて外部からの充電も可能なため、自宅に充電設備を設置することでさらに利便性が向上します。
自宅に充電設備を設置するためのコストをみてみましょう。充電用設備は3つのタイプがあります。
- 自立スタンドタイプ「価格帯:25万円~」
- 商業施設や公共施設に設置されていることが多いタイプです。自宅と駐車場が離れた場所にある場合でも設置ができます。
- 壁掛けタイプ(ボックス)「価格帯:15万円~」
- 壁に取り付けるタイプで、自立スタンドタイプよりも価格を安く抑えられます。自宅と駐車場の距離が近い場合に設置可能です。
- コンセントタイプ「価格帯:数千円~」
- シンプルなつくりで、コンパクトサイズなのが特徴です。充電の都度、車載ケーブルの出し入れが必要ですが、価格帯がもっとも安いタイプです。
充電設備を自宅に設置することで、充電スポットやガソリンスタンドに行く必要もなく時間や労力をかけずにすみます。
EVは補助金の活用が可能
電気自動車は車体価格が高額傾向ではあるものの、購入する際はガソリン車よりも多くの補助金が受けられます。環境への配慮から国や自治体は電気自動車を促進しており、国と自治体それぞれが補助金制度を設けています。
国の補助金「CEV補助金」
CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)は、国が地球の環境改善に取り組むために設けている補助金制度です。条件や上限金額は毎年更新されるため、その都度最新の情報を調べる必要があります。2024年度に関しては、以下のように上限額が設定されています。
【令和6年度(2024年度)の補助金上限】
| 対象の車種 | 補助金上限 |
|---|---|
| 電気自動車(EV) | 85万円 |
| 軽EV・プラグインハイブリット(PHV) | 55万円 |
種類によって最大85万円の補助金を受けられるため、購入価格のコストカットが可能です。ただし、補助金を受けるには一定の期間内に新車で購入することが条件となり、申請期間や申請方法なども決まっています。購入の際はディーラーなどにも相談し、情報を調べることをおすすめします。
自治体の補助金
国の補助金とは別に、地方自治体の補助金の併用も可能です。東京都を例に紹介すると、令和5年度(2023年度)の電気自動車(EV)の基本補助額は45万円でした。車種などの条件によっては、上乗せ補助額が加算されるケースもあります。
CEV補助金と併用すると大きな補助金となるため、車体価格が高くても補助金を活用することで大幅にコストカットが可能です。ただし、自治体ごとに補助金の条件や上限額は異なるため、国の補助金と同じく各自治体のホームページにて詳細を確認する必要があります。
また、自宅に充電設備を設置する場合も、自治体の補助金の対象となるケースもあるため合わせて確認するとよいでしょう。
まとめ
電気自動車は車体価格が割高な傾向がありますが、国や自治体の補助金制度を活用すればガソリン車との価格差の問題は解消できます。
また、走行距離で比較するランニングコストや税金の面から長期的にみて判断すると、電気自動車のほうがお得です。電気自動車は街中の充電スタンドも充実し、自宅用の充電設備もさまざまなタイプが登場していることから、今後さらに実用性の向上も期待できます。車体価格だけではなく、さまざま面で検討してみるとよいでしょう。
関連記事

いざ、マンションにEV充電器を設置しようと思っても、まず何から始めたらよいのかわからないという方は多いでしょう。今回は、マンション・アパートへのEV充電器の設置方法を紹介するとともに、その際に発生すると考えられる問題点について解説します。 あらかじめ知っているのといないのでは、実際導入するときに大きな差となります。知っておくべきポイントを理解することで、スムーズに導入することが可能です。EV充電器の設置を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

EV・HV・PHV・FCVの違いとは?知っておきたい4種の電気自動車の種類
地球環境に優しいエコな自動車であるEV(電気自動車)は、国内外問わず多くの自動車メーカーが開発をおこない、普及が進んでいます。EVにもさまざまな種類があるため、「買い換えを検討しているけれど、どのような違いがあるのかよくわからない」という方も多いのではないでしょうか。 この記事では、EV・HV・PHV・FCVのそれぞれの特徴やメリット・デメリットについて紹介します。
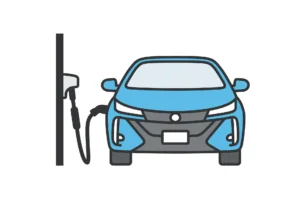
EV・PHEV充電用コンセントとは?メリットや設置前の注意点を解説
近年、電気自動車(EV)の普及と高ガソリン価格で、多くの人が購入を考えています。自宅での充電は大きな利点ですが、充電器の種類や設置に関する問題もあります。この記事では、家庭用EV充電器の特徴、設置のメリット・デメリットと注意点を解説します。

電気自動車(EV)の需要が高まる中、充電方法が気になる方が増えてきました。自宅充電のメリット・デメリットから充電器の種類、設置の注意点まで、この記事で詳しく説明します。家庭用EV充電器を考えている方は、ぜひご覧ください。

EV・PHEV充電器のおすすめ商品を比較!選び方やメーカー別特徴も紹介
電気自動車の購入を検討するにあたり、稼働するためのEV・PHEV充電器の設置も検討している方が増えてきています。この記事では、EV充電器のおすすめ商品を比較し、選び方やメーカー別の特徴についてご紹介します。